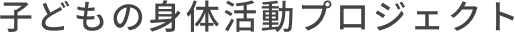事例紹介

佐久市立東小学校(元:佐久市立野沢小学校) 養護教諭 錦織志子先生
近年、運動しない子どもが多いと言われておりますが、数値として客観的にそれを示すことが小学校でどのように行えるのか手立てが無く悩んでおりましたところ、2019年度の養護教諭部会で城所先生より身体活動調査のご紹介がありました。活動量計を装着することで、子どもたちの身体活動量が測れるということで、本校での身体活動調査を開始いたしました。身体活動量の平均値も大切ではありますが、児童自身それぞれがどのぐらいの身体活動量(各自の傾向)であるかを計り、個人にフィードバックしていただくことで児童自身と家庭で生活を見直す機会を作ることができました。本校ではこの調査を4~6年生で実施しているため、自分の経年データを追うこともでき、生活の見直しに大きく役立っております。また、本校では、新型コロナウィルス流行前の2019年より活動量調査に参加しているため、コロナ禍における身体活動量の減少を数値として明確に把握することができました。それを児童や保護者に示すことができましたので、「これではいけない」という意識が高まり、新型コロナウィルス収束後は身体活動量がV字回復をしてまいりました。個人と学校全体の平均値のデータを見比べる事ができますので、漠然と「外に出よう」「運動しよう」という声がけだけでなく、このような具体的なデータを通して、児童自身と保護者が子どもの時から体を動かすことを習慣化する意識付けに大きく役立ちました。万歩計のような機械を1週間つけておくだけで、データがとれる手軽さも学校で進め易い特徴であり、本校で継続できた理由の一つだと思います。この身体活動調査を多くの先生方に知っていただき、活用していただきたいと思っております。

八王子市立宇津木台小学校(元:八王子市立第七小学校) 校長 松丸渉先生
八王子市立第七小学校では、令和5~6年度に東京都教育委員会体育健康教育推進校の指定を受け、体育の授業改善、運動の日常化、食育・保健指導等、健康教育の充実に取り組んでまいりました。運動の日常化については、今井夏子先生にご協力いただき、1年間にわたり休み時間や体育的活動の取組期間中の「遊び場調査」を実施していただきました。その調査から、どのくらいの人数の子供たちが校庭に出ていて、どのような場所でどのような遊びを行っているのかを分析していただいたことで、高学年になるにつれて校庭で遊んでいる児童が減少することや遊びの種類の少なさが明確となってきました。本校では、その課題を解消するために、遊び時間の創出、遊び用具や遊び場の環境整備、遊びを広げるための掲示物の作成、委員会活動を活用した遊びの取組、体育的活動の工夫改善等、様々な取組を行ってきました。その結果、校庭で遊ぶ児童の割合や遊びの種類が増加する等、多くの成果が見られました。今後の課題は、高学年の外遊びをさらに増やしていくことです。この「遊び場調査」は、児童の実態が数値で明らかになることで課題や成果が明確になり、改善策を焦点化して考え実践することができるので、健康的な児童を育成するにあたり、大変効果的であると思います。

長野県東御市(公財)身体教育医学研究所 所長 岡田真平先生
長野県東御市では、令和6年度に市内全5小学校の遊び場調査を実施していただきました。調査実施にあたり、まずは、市の教育長や指導主事、市役所職員ほか関係メンバーで事前学習の機会を持ちましたが、そこで、研究チームの思いや実績、目指している方向性を皆で拝聴・共有して、共感と期待を抱いたことから、全校実施の方針を即決することができました。各学校への依頼も、校長会の了解の後、各校への訪問相談(教頭への説明)は研究チームにもお越しいただき、スムーズに調整を進めることができました。現場負担が無い、という調査手法の強みも大きかったと思いますが、何より「子どもたちが学校で元気に過ごし、健やかに育ってもらいたい!」という、教育現場なら誰もが望む願いを叶える取り組みである、と皆が感じたことが大きかったと思います。校庭等での観察調査ということで、児童や家庭の理解も不可欠でしたが、学校の全面的な協力もあり、保護者の方々への事前周知でも大きな問題はありませんでした。東御市では長く、児童生徒の体力向上・健康支援活動に取り組んできましたが、「体力向上を子どもたちに押し付けることが運動嫌いや体力・健康格差を助長してしまうのでは…」という悩み・ジレンマを抱えながらの試行錯誤でした。今後は、児童・家庭・学校現場への温かい眼差しが基盤にあるこの調査の力を借りながら、より良い支援を模索・構築していきたいと思っています。
研究体制

研究統括:
城所哲宏(日本体育大学体育学部・准教授)
共同研究者:
今井夏子(株式会社コミュニティネット・研究員)